「うちの子、ADHDかも?」小学一年生の子育てで感じるグレーゾーンとの向き合い方
「うちの子、もしかしてADHDかも?」
小学一年生のわが子を見ていて、ふとそんな不安がよぎることがあります。
- すぐにイライラして怒ってしまう
- 気がついたらひとりで歌っている
- ご飯の食べこぼしがひどい
- 一人になりたがる
- 人形遊びをひとりでぶつぶつ言いながらしている
一見すると「ちょっと個性的な子かな?」と思うかもしれませんが、育てている親としては「周りと違うような気がする」「もしかして発達障害かも?」と不安になることもありますよね。
この記事では、わが子の特性に悩みながらも前向きに向き合ってきた私の視点から、「グレーゾーンかもしれない子どもへの関わり方」について、わかりやすくまとめました。
ADHDとは?基本的な特徴
ADHD(注意欠如・多動性障害)は、主に以下のような特徴があります。
- 不注意:集中が続かない、忘れ物が多い、指示を聞き漏らす
- 多動性:じっとしていられない、しゃべりすぎる
- 衝動性:順番が待てない、思ったことをすぐ口にしてしまう
ただし、これらは「診断がつくレベル」であれば日常生活に支障が出るほど強く現れます。
単に「ちょっと落ち着きがない」「よくしゃべる」といった程度であれば、性格や成長の個人差であることも多いのです。
わが子の様子|当てはまるけど、ちょっと違う?
わが子もいくつかの特徴が当てはまります。
1. 集中力があるけど、切り替えが苦手
「ADHDは集中力がない」というイメージがあるかもしれませんが、うちの子はむしろ集中力が高いタイプ。
好きなことには何時間でも夢中になっていて、とくに歌をうたったり、絵を描いたり、人形遊びをしているときは別世界にいるようです。でも、そこから現実に戻る「切り替え」が難しく、「今ごはんだよ」「片付けて」と言ってもなかなか動けません。
2. 一人で人形遊び、ぶつぶつしゃべっている
人形遊びを一人でして、ぶつぶつと独り言を言っている姿。最初は少し心配になりました。
でもこれは、「想像力が豊か」「気持ちを整理している」「自分の世界に安心感を感じている」など、ポジティブな面も多い行動だと知り、今は見守るようにしています。
3. 食事中の食べこぼしがひどい
食事のときに、よくこぼす・姿勢が崩れる・お皿に集中できない、といった様子もあります。
これは感覚の過敏さや不器用さ、注意の向け方に特性がある場合によく見られるそうで、「何度言っても治らない!」と叱るより、環境を整えてサポートすることが大事だと感じています。
「グレーゾーン」とは?ADHDじゃないけど育てにくい…
診断がつくほどではないけれど、「ちょっと育てにくさがある」「周りの子と違う気がする」。
そんなとき、子どもは**「発達グレーゾーン」**にあたる場合があります。
グレーゾーンの子の特徴
- 集団生活でトラブルが起きやすい
- 集中・切り替え・感情のコントロールが苦手
- 興味の偏りが強い
- 感覚が敏感だったり、鈍感だったりする
ただし、「個性の範囲」と紙一重なことも多く、専門家でも判断が難しい領域です。
診断がつかないからといって「問題がない」わけでもなく、「サポートが必要じゃない」とも限りません。
グレーゾーンの子にできる関わり方
では、実際にどんな風に関わっていけばいいのでしょうか。
1. 「困っている行動」を責めない
つい「何度言ったらわかるの!」「ちゃんとして!」と言いたくなりますが、叱っても本人も「うまくできない」ことで悩んでいることが多いです。
「どうしてできないの?」ではなく、「どうしたらやりやすくなるか?」の視点で関わることが大切です。
2. 生活の中で工夫する
- ご飯のときは深めのお皿にして、すくいやすくする
- 座る場所に滑り止めを敷く
- 怒りやすいときは、まず気持ちを代弁して落ち着かせる
- 切り替えが苦手なときは、「あと5分ね」「3回数えたらやめよう」など視覚や聴覚でサポートする
3. 「得意」を大切に育てる
興味のあることに集中できるのは、グレーゾーンの子の大きな強みです。
「歌が好き」「絵が好き」「工作が得意」など、その子の世界を否定せず、好きなことを伸ばしていくことが自信にもつながります。
専門機関への相談も、選択肢のひとつ
「これって普通?」「うちだけ?」とモヤモヤすることがあれば、相談機関に話を聞いてもらうのもアリです。
- 小児科・発達外来
- 市区町村の発達相談窓口
- 児童発達支援センター
- スクールカウンセラー
相談したからといって、すぐに診断や支援が決まるわけではありません。
「お母さんひとりで抱えないでいいよ」という意味でも、頼れる場所を知っておくことは大切です。
まとめ|「ちょっと育てにくい」の奥には、たくさんの才能がある
わが子を育てていて、「なんでこの子はこうなんだろう?」と悩むことはたくさんあります。
でも、その“ちょっと育てにくい部分”の奥には、その子にしかない個性や才能が必ずあると思っています。
ADHDかどうかにこだわるよりも、
「目の前のこの子を、どうやって生きやすくしてあげられるか」
その視点が、親にできる一番のサポートだと、私は信じています。
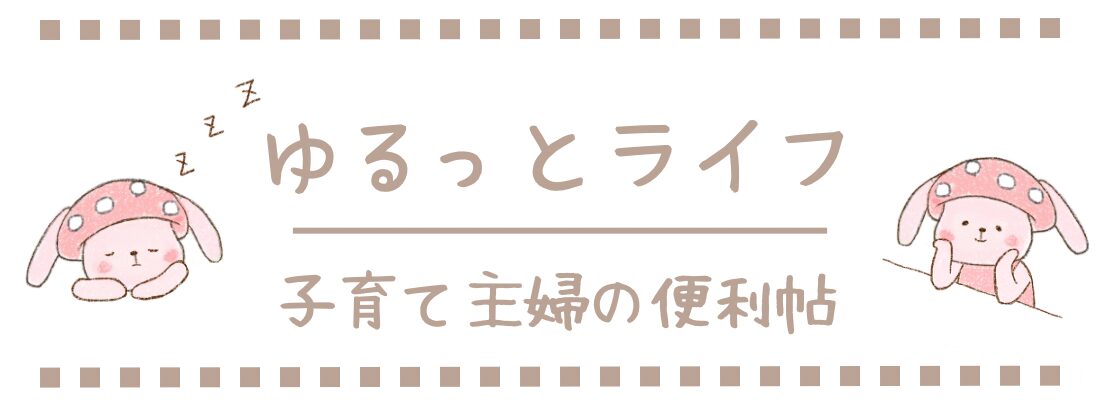



コメント