こんにちは、ゆるママです。
子どもが小学校に入学すると、新しい環境・新しい生活リズムで、親もバタバタしますよね。
その中でも多くのママが悩むのが…
「登下校の送り迎えって、いつまで続けたらいいの?」
という問題。
最初は心配だから毎日送り迎え。でも、いつかはひとりで通えるようになってほしい。どこで見守りをやめるか、なかなか判断が難しいですよね。
今回は、実際のママたちの声や体験談、わが家のケースを交えながら、「送り迎え、いつまで?」のヒントをお伝えしていきます。
小学1年生の登下校は不安がいっぱい

小学生になったばかりの子どもは、こんなことに戸惑います。
- 朝の支度が間に合わない
- 通学路がまだ覚えられない
- 交通ルールを理解していても実践が難しい
- 「ひとりで歩く」こと自体に慣れていない
親としても、
- 事故に遭わないかな…
- 通学路に不審者が出ないかな…
- 学校までちゃんと行けるかな…
と心配が尽きませんよね。
そのため、多くの家庭では最初の1ヶ月〜3ヶ月ほどは送り迎えをしているのが現状です。
送り迎え、みんないつまでしてるの?

ママ友やSNS、学校の先生に聞いた話をまとめると、こんな感じです。
| 続けた期間 | 割合・意見 |
| 1ヶ月程度 | 「慣れてきたら徐々に手放した」派 |
| 夏休み前まで | 「1学期は続けた」派 |
| 小1の1年間 | 「その子の性格による」「心配だったから」 |
| 小2まで | 「妹や弟の送り迎えと一緒に継続」 |
| 毎日ではなく見守りだけ | 「登校だけ一緒に歩く」「家から見送るだけ」派も多数 |
見極めポイントは「子どもの様子+通学環境」

いつまで送り迎えを続けるかを決めるには、以下のような視点が大切です。
通学距離・道の安全性
- 交通量が多い
- 歩道が狭い
- 信号が少ない
- 一人で通う子が少ない
こういった場合は、見守りを長めに続けるご家庭が多いです。
子どもの性格
- 慎重で怖がり → 時間をかけて見守り
- 活発だけど注意力に欠ける → しっかり確認
- 自信がついてきた → 少しずつ一人歩きを練習
集団登校があるか
地域によっては、近所の子と班を組んで登校する「集団登校」があるところも。これがあると、比較的安心して見送りをやめることができます。
わが家のケース:段階的にステップダウン

うちの子は最初、少し不安そうに登校していました。
しかし集団下校が終わり、1ヶ月ほど経って道も覚え、5月からはお迎えいかず。
帰ってきたらいつもインターホンを押し「ママーただいま〜!」と笑顔で帰ってくるように。
そこで、わが家はこのように段階的に送り迎えを減らしていきました。
【登校】
- 最初の1週間:学校の門まで一緒に
- 2週目以降:途中の交差点まで見送り
- 1ヶ月後:家から「行ってらっしゃい」で見守り
【下校】
- 1ヶ月間はお迎え必須
- 学校からの「ひとり下校OK」のサイン後、時間だけ決めて帰宅
- GPSつきキッズ携帯を活用して安全確認
子どもの「やってみたい」という気持ちと、親の「心配」を両立させながら、少しずつ手を離す感じでした。
無理に急がなくて大丈夫

「周りはもう送り迎えしてないのに…」「甘やかしすぎかも…」と焦る必要はありません。
小1の時期は、まだまだ「守ってあげたい時期」。
特に春は交通事故が多く、警察庁のデータでも「新1年生の事故件数は4月・5月が最多」とされています。
子どもに安心感を与えつつ、自立心を育てるステップとして、送り迎えを上手に活用していきましょう。
安心して一人で登下校させるための工夫

送り迎えを卒業する際に取り入れたい対策はこちら:
- GPSをもたせる(みてねみまもりGPSなど)←本当に買ってよかった!トーク機能付きがおすすめ
- 通学路の危険箇所を一緒に確認
- 毎日の登下校時間を記録する(親の安心材料に)
- 防犯ブザーの使い方を練習
- 「困ったとき駆け込めるお店や家」を覚えさせる
■「みてねみまもりGPS」が気になる方はこちらの記事もおすすめです
👉 【レビュー】みてねみまもりGPSは買ってよかった?小1ママのリアルな感想
まとめ 送り迎えの卒業時期に正解はない!

子どもの性格、住んでいる場所、通学ルートなどによって、ベストなタイミングは違います。
「○月までに一人で行かせなきゃ」とプレッシャーを感じずに、“わが家なりのペース”でOKです。
親子で話し合いながら、ちょっとずつ「自分でできた!」を増やしていく。
それが、子どもの自信にもつながっていくはずです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
このブログでは「ママがゆるっと安心して子育てできるヒント」を発信しています。
同じように悩むママの心が少しでも軽くなりますように。
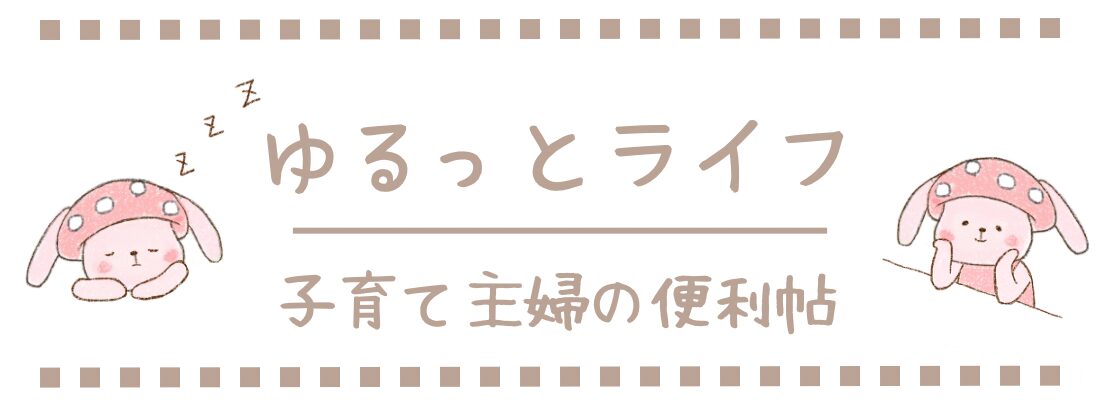



コメント